日 時|2025年3月19日 (水) 13:30–16:00
会 場|多摩美術大学アートとデザインの人類学研究所
多摩美術大学アートとデザインの人類学研究所では、本学図書館との共催にて公開研究会「折口信夫を読む」を開催いたします。

なぜ、いま折口信夫なのか
民俗学者にして国文学者でもある折口信夫(1887-1953)は、専門の領域を超え、現代日本の文学(三島由紀夫、大江健三郎、中上健次)、さらには現代日本の諸芸術(建築、音楽、演劇、舞踏)に大きな影響を、現在でも与え続けている。折口は本名を用いて研究を行ない、釈迢空という特異な筆名を用いて短歌・詩・小説・戯曲、つまりは日本語に許されている創作のすべてのジャンルで独創的な作品群を残した。同時代のヨーロッパに勃興した新たな学問、人類学や民族学の著作のエッセンスも貪欲に吸収していた。研究者にして創作者であった。詩と論理とを両立させるその表現の在り方に激しい批判も浴びたが、しかし、新たな表現を求める者たちは、折口が表現者として維持し続けていたそうした姿勢をつねに参照している。折口が遺してくれた膨大なテクストこそ現代文学の隠された一つの始原であり、現代芸術の隠された一つの始原である。
時間と空間を定めて彼方の世界からこの地上を訪れ、旧い時間と空間を滅ぼすとともに新たにそれらをよみがえらせる存在を、折口は「まれびと」と名づけた。「まれびと」は神にして人であり、無限にして永遠の世界と有限にして瞬間の世界、「もの」(物質)と生命という相矛盾する二つの極を、その相矛盾するがまま一つにむすび合せる。折口が南島で目にした「まれびと」は、巨大な獣のような身体に野生の草木の衣装をまとい、鉱物質の異様な仮面をつけていた。動物、植物、鉱物といった種の差異が無化され、同時に男性と女性という性の差異、老人(翁)と嬰児という世代の差異も無化される。「まれびと」たちは祝祭をもたらし、祝祭の中心となり、踊り、歌い、遠い過去に生起した世界の創世をいまここで繰り返す。反復と生成に区別がつけられない無垢なる世界が、祝祭とともに現成する。そうした祝祭の最中、死者たちはよみがえり、生者たちと一つに交わる。
折口信夫は、神話と「歴史」の再考を促し、祝祭と「場所」の再考を促し、物質と「生命」の再考を促し、性と「身体」の再考を促し、呪術と「言語」の再考を促し、文学を含めた芸術表現すべての再考を促し続けている。いまここに、あらためて折口信夫の営為を再考するとともに再興し、解体するとともに再構築する研究会を組織する。
安藤礼二
批評家|図書館情報センター長
————————————
◉開催概要
講 師 安藤礼二 (批評家、芸術学科教授、図書館情報センター長)
仁科 斂(小説家、来期より芸術学科非常勤講師)
石橋直樹(批評家)
日 時 2025年3月19日(水)13:30〜16:00(開場 13:10)
会 場 多摩美術大学 八王子キャンパス・アートとデザインの人類学研究所(アクセス)
対 象 本学学生・教職員、学外一般
※参加自由 / 事前申込不要(当日会場にて記帳をお願いします)。
※定員は40名程度。満席の際は入場をお断りする場合があります。
————————————
◉発表タイトル
安藤礼二 「天皇の解体と再構築 折口信夫と出口王仁三郎」
仁科 斂 「文体試論:寂しさの存在(論)的差異」
石橋直樹 「後期折口信夫へ至る三つの行路ー憲法・歴史・国学」
※発表の後、討議と質疑応答を予定しています。
————————————
◉講師プロフィール

安藤礼二 Reiji Ando
多摩美術大学芸術学科教授、図書館情報センター長。主著に『神々の闘争 折口信夫論』『折口信夫』『大拙』『列島祝祭論』『縄文論』『井筒俊彦 起源の哲学』など多数。

仁科 斂 Wren Nishina
1994年生まれ。「さびしさは一個の廃墟」で新潮新人文学賞受賞(2024年11月号)。ハンナ・アーレントと折口信夫を研究。受賞作は磯崎新の「廃墟」も論じられている。
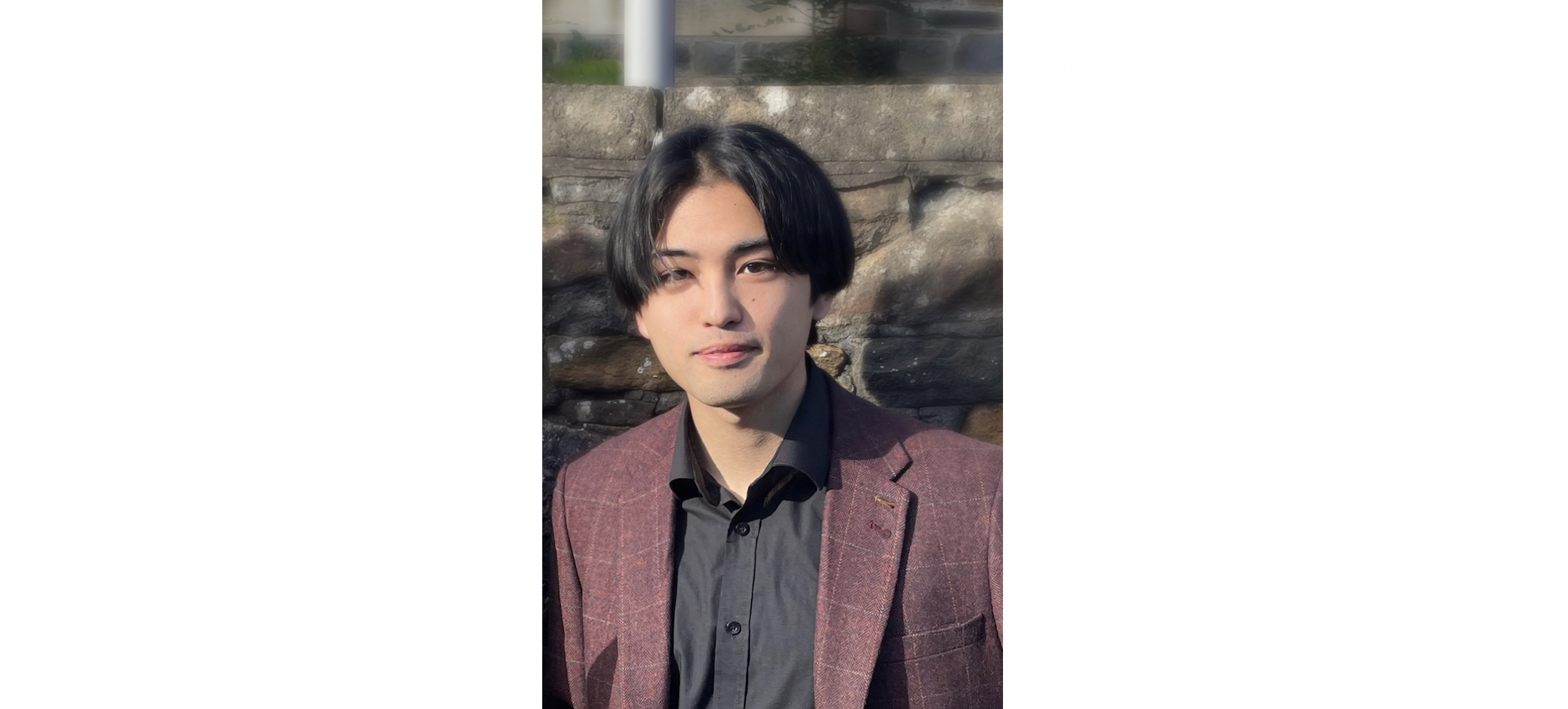
石橋直樹 Naoki Ishibashi
2001年生まれ。「〈残存〉の彼方へ 折口信夫の「あたゐずむ」から」で三田文學新人賞受賞(2023年春季号)。近代の民俗学とともに近世の国学、平田篤胤なども研究。
————————————
お問い合わせ
多摩美術大学アートとデザインの人類学研究所
〒192-0394 東京都八王子市鑓水 2-1723 メディアセンター4F
Email:iaa_info@tamabi.ac.jp